嗅覚は私たちの日常に深く関わっている感覚の一つです。しかし、ストレスや年齢とともに、嗅覚が鈍くなることもあります。そんな時、簡単でお金をかけずに嗅覚を鍛える方法があれば嬉しいですよね。実は、嗅覚を鍛えるために必要なのは、特別な高額アイテムではなく、ちょっとした工夫と実践です。
この記事では、お金をかけずにできる嗅覚トレーニングの方法を紹介し、その効果を高めるためにおすすめのアロマ精油とその使い方も紹介します。
▷ 嗅覚の重要性
▷ お金をかけずにできる嗅覚トレーニングのやり方
・自宅にあるものでできる簡単なトレーニング
▷ アロマ精油を使った嗅覚トレーニング
・おすすめのアロマ精油
・トレーニング方法
・精油の種類に決まりはある?
・精油を使う時の注意事項
▷ まとめ
嗅覚の重要性

「嗅覚」は人が香りを感知するために重要な感覚です。食べ物の味を感じたり、危険な物質のにおいを感じとるためにも嗅覚は重要ですし、リラックスや記憶にも嗅覚は関わっています。しかし、加齢やストレス、慢性の鼻詰まり、風邪などウイルス感染、病気などによって感覚が鈍ることがあります。
嗅覚トレーニングは、嗅覚の低下を感じている方、嗅覚の低下を予防したいという方におすすめのトレーニング法です。嗅覚を鍛えることで、食事の楽しさが増すだけでなく、精神的なリラックス・リフレッシュにも繋がり、日常生活の質が向上します。
お金をかけずにできる嗅覚トレーニングのやり方

お金をかけずに嗅覚トレーニングをするなら、身の回りのにおいをとにかく意識して嗅ぐのがおすすめです。一時的ににおいを感じなくなったという時は、香りを思い出しながらにおいを嗅ぐという方法もあります。
例えば、レモンを買ったら『これはレモンの酸っぱいにおい』と思い出しながらにおいを嗅ぐ、
雨上がりの草の上を歩くなら『ここは雨が降ったあとの土と草のにおい』と思ってにおいを嗅ぐ、
ミスドの前を通ったら『大好きな甘いドーナツのにおい』を思い出しながらにおいを嗅ぐ、
夕飯にカレーが出たら『辛口の、スパイシーで食欲が出るにおい』と思ってにおいを嗅ぐ、
というように、においを意識して嗅ぐことで、においを感じる細胞の再生と症状改善が期待できると言われています。
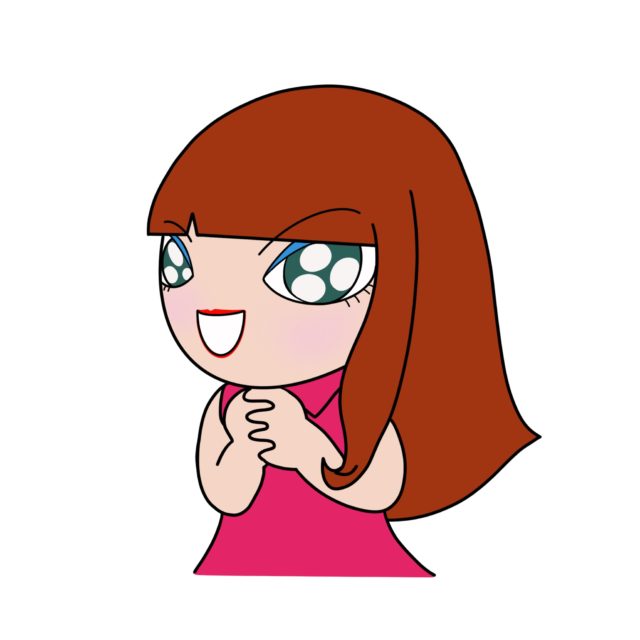
自宅にあるものでできる簡単なトレーニング

お金をかけずに嗅覚を鍛えたいなら、自宅のキッチンにある調味料がおすすめです。例えば、レモン、コーヒー、バニラ、ミント、シナモンなど。
step
1それぞれの香り(レモン、コーヒー、バニラ、ミント、シナモンなど)を1〜2分ずつ嗅ぎ、香りをしっかり覚えます。
step
2目を閉じ、香りを一つずつ嗅ぎ、どの香りかを当てます。
step
3これを1日1回、繰り返します。

Karisugi母の経験談を少し・・・
Karisugiの母は、コロナ渦よりずっと前に、嗅覚がなくなった時期がありました。
においが全くしない、肉を食べてもゴムを食べているような食感しかしない、いつ治るかわからない、体力・生命維持のためだけの無味無感動な食生活。それがなんと約1年半も続きました。
原因はわかりません。というのは、嗅覚がなくなった原因を調べに病院へ行かなかったので、心当たりはあっても断言できないためです。嗅覚を取り戻すための治療もしていませんでした。
嗅覚がない期間は、においがするかどうか、なんでもクンクン嗅いでいたそうです。もう無意識ですね。
1年半ほど経ち、無臭だったのが焦げ臭いにおいを感じるようになり、そこから、かすかに香りを感じる瞬間が増えていき、いつの間にか治った...ということがありました。
においを全く感じなくなってから1年半後の嗅覚復活!こういう事例もあるということで...。
アロマ精油を使った嗅覚トレーニング
美容や心身のリラクゼーション、セルフケアに役立てられるアロマですが、嗅覚トレーニングでも、香りの刺激を与えることで、嗅覚の衰え予防に役立つと期待されています。
ここからは、嗅覚トレーニングにおすすめのアロマ精油とその使い方について紹介します。
おすすめのアロマ精油

一般的な嗅覚トレーニングにおすすめのアロマ(精油)は、樹脂臭(ユーカリ)、薬味臭(クローブ)、果実香(レモン)、花香(バラやラベンダー)です。
生活の木では、花香にラベンダー・フランス産を使用していますが、ドイツの研究ではバラを使用しています。

トレーニング方法
トレーニング方法には、ご自身のお手持ちの精油で行う方法と、「生活の木」の嗅覚トレーニングセットで行う方法があります。
まずは、お手持ちの精油を使ったトレーニング方法を紹介します。
step
1精油を1〜2滴、ティッシュやコットンに垂らします。
step
2目を閉じて、香りを深く吸い込み、香りの特徴を感じとります。
step
3数回繰り返すことで、香りの記憶を強化します。

次に、生活の木で紹介しているトレーニング方法を紹介します。
『生活の木』の嗅覚トレーニング
* 1回5分程度でできるトレーニングです。
* 4種の異なる精油を、朝と晩の1日2回、約10秒嗅ぎます。これを12週間続けます。
材料
● クリーム容器型の遮光瓶:4個
● コットン:4枚
● 容器に貼るシール:4枚
● ユーカリ・グロブルス:20滴
● クローブ:20滴
● レモン:20滴
● ラベンダー・フランス産:20滴
※ 瓶の口が広い(大きい)ものを使うと香りをよく感じます。遮光瓶を使うのは、保存性の面で適しているからです。
前準備
【1】4個の遮光瓶にコットンを1枚ずつ入れます。
【2】コットンに染み込ませるようにユーカリ・グロブルス精油を20滴入れたら蓋をします。クローブ、レモン、ラベンダーも同じように作ります。
【3】精油名を書いたシールをそれぞれ遮光瓶に貼ります。
嗅覚トレーニングのやり方
アロマはどの香りから嗅いでもOK。
step
1蓋を開けて、鼻から3cmほど離した位置でビンを持つ。
step
2口を閉じ、深呼吸をするのではなく、鼻からくんくん小さく嗅ぐ(10秒間続ける)。
嗅いでいるときは、何のアロマを嗅いでいるのか意識しましょう。
step
3嗅ぎ終わったら、ビンの蓋を閉めて、1分間ほどリラックスして休む。
1種類につき10秒間嗅ぎ、その都度1分ほど休みましょう。
step
4残りの精油も1〜3を繰り返す。計4種類の香りを嗅ぐ。
step
5これを朝晩2回、12週間続ける。
引用:1回5分でできる 4種のアロマで嗅覚トレーニングのやり方|生活の木
新鮮な精油の香りを1回ごとに嗅ぎたいときは、ムエットがおすすめです。朝晩2回・12週間使ってもじゅうぶん余るし、また必要になったときのために予備として残しておくと良いですよ。
-

香りをもっと自由に楽しむ!カード型ムエットの活用法と簡単DIYアイデア
香水やアロマを楽しむとき、「香りの違いを比べたい」「人に香りを伝えたい」と思ったことはありませんか? そんなときに活躍するのがカード型ムエット。 実は今、香りのサンプルやイベントのプチギフトとしても人 ...
精油の種類に決まりはある?

嗅覚トレーニングに使う香り(精油)は、バラやラベンダー、クローブ、ユーカリ、レモンが主です。
ほかに、ペパーミント、ジャスミン、タイム、ローズマリー、ベルガモットなども使われていることから、必ずしも決まった香りを使わないとダメということではないようです。
また、精油(エッセンシャルオイル)の代わりにアロマオイルを使うこともでき、要は何の香りなのか意識しながら嗅ぐことが重要みたいですね。
ただ、実際研究に使われ、かつ改善が見られた精油として、バラ、クローブ、ユーカリ、レモンが知られているため、嗅覚トレーニングを始めようとする方に勧められるのだと思います。
ちなみにアロマオイルはアルコールなどで希釈されていて、主に芳香浴に使われます。精油(エッセンシャルオイル)とは違うものなので、購入の際はご注意ください。 良質な精油を選ぶためには、信頼できるメーカーの製品を選び、目的に応じて自分に合った精油を選ぶことが大切です。 精油は心身に良い影響を与えると言われていますが、正しい選び方をしないとその効果を最大限に ...

信頼できる精油メーカーと選び方 - メディカルアロマに使える精油も紹介!
精油を使う時の注意事項
精油は飲めません。飲んでしまった場合はすぐに医師の診断を受けましょう。
精油のふたを開けたままにすると劣化が進んでしまいます。精油のにおいを嗅ぐときは、直接瓶から嗅ぐのではなく、ムエットなどを使い、精油のふたはなるべく早く閉めましょう。
精油をそのまま皮膚や粘膜につけることはできません。お肌に使う場合は必ずホホバオイルなどキャリアオイルか、無水エタノールと精製水に混ぜてご使用ください。
精油は光や熱に弱いので、冷暗所で保管しましょう。また、瓶は横にせず、立てて保管することが望ましいです。
精油は揮発性が高く引火の可能性があるものなので、使用時は火器にご注意ください。
まとめ
嗅覚トレーニングは日常に簡単に取り入れることができ、身近にある香りやアロマ精油を使うことで、嗅覚の衰え予防や改善が期待できます。
アロマ精油を使う場合は多少お金はかかってしまいますが、それぞれの精油には特有の効果があり、嗅覚トレーニングを行いながら心身をリフレッシュできるというメリットもあります。
いずれにしても、香りの刺激を与えることで、嗅覚の衰え予防に役立つと期待されているので、嗅覚の低下を予防したい方や、嗅覚が鈍くなったと感じる方は、ぜひ取り入れてみてください。
-

アロマで認知機能改善?高齢者におすすめのアロマケアを紹介!
認知症の中でも特に多いアルツハイマー型認知症に、アロマテラピーが有用であることをご存知でしょうか。アルツハイマー型認知症は、初期症状として物忘れより前ににおいが分かりにくくなるという特徴があります。 ...
-

黒胡椒の香りで嚥下をサポート!アロマパッチの効果と使い方を紹介
「食べ物や飲み物がうまく飲み込めない…」「むせやすくなってきた…」 そんな嚥下の悩みを抱える方に、今“香りの力”が注目されています。 中でも、黒胡椒の香りを使った「アロマパッチ」が、嚥下反射を促すサポ ...
-

精油は“立てて”保管が基本!収納におすすめの木箱・ポーチ・持ち運びケースを紹介!
お気に入りの精油やアロマオイル、気づけばどんどん増えていませんか? 精油は“光・熱・酸素”に弱く、保管状態によっては劣化してしまうことがあります。 さらに、横に倒して保管するとキャップから漏れたり、ド ...
-

選ぶ香りで体質がわかる?嗅覚反応分析とは〜心と体の健康チェックに
嗅覚反応分析とは、簡単に言うと、特定の香りを嗅いで、その好き嫌いをチェックして、心や体の状態を分析するというものです。 以前は「サードメディスン」と呼ばれていました。 嗅覚は、心と体、感 ...
-

精油の香りは血圧に影響するって本当?【個人的に測ってみた】
精油の中には、"血圧を上げるので高血圧の方は禁忌" と言われるものがあります。逆に、"血圧を下げるので低血圧の方は控えたほうがいい" というものもあります。 個人的には精油を単品で使うことはほとんどな ...
-

たった10秒で感じるアロマ精油の効果!シーン別おすすめ精油と使い方
仕事や家事で疲れた時に、アロマ精油の香りをかぐだけでリフレッシュできたらいいと思いませんか? たった10秒アロマの香りをかぐだけでも、心身のリラックスやリフレッシュに役立ちます。『こんな時はこの香り ...
-

グレープフルーツの香りでダイエットをサポート!精油の成分、効果、活用法も紹介
グレープフルーツの爽やかな香りには、心と体に嬉しい効果がたくさんあります。特に注目したいのは、ダイエットに役立つと言われる効果。グレープフルーツ精油には、脂肪燃焼を促進する香り成分が含まれており、気分 ...
-

冬に欲しい甘い香り〜香水、キャンドル、アロマ、リップおすすめを紹介!
寒いと甘いものが食べたくなるように、甘い香りが欲しくなることはありませんか。 甘いものが欲しくなる理由は、疲れや気分の落ち込み、イライラやストレス、自律神経の乱れ、あと、単純にエネルギーを作るために ...
この記事を書いた人

主にアロマテラピーやCBDを用いたセルフケアに関する記事を発信。医療系、アロマテラピー、CBDの資格保持。人間の大敵「ストレス」を緩和する方法やアイテムを紹介している。ほかにも美容・健康、資格に関することなどのんびり更新中。










